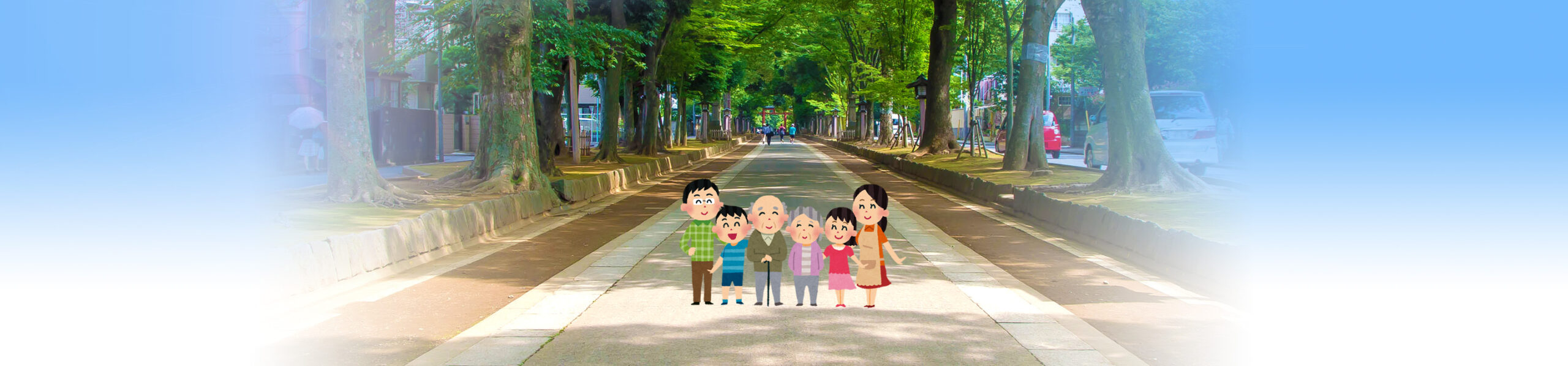自分が亡くなった後に、残された家族が自分の相続で争い、争族にならないように、生前のうちから争族や相続税などの対策を行う「生前対策」が重要視されています。
しかし、実は生前対策は生きているうちであればいつでも良いというわけではないのです。
生前対策としてよく耳にする生前贈与や遺言などは、認知症になってしまった後では行うことができません。ですから、認知症になる前に、あなたやあなたの家族にとって必要なできる限りの生前対策を行っておくことが大切なのです。
今回は、認知症になる前にしておくべき生前対策をいくつかご紹介いたします。残される家族にとってどのような対策を取ることができるか、この記事を参考に考えてみてください。
認知症になると相続対策ができなくなる
認知症により判断能力が低下すると、遺言を書いたり、持っている不動産の売却をしたりといった法律行為ができなくなってしまいます。認知症になった後、一時的に判断能力が回復することはありますが、基本的に相続対策はできなくなると考えた方が良いでしょう。
例えば、自分以外に自宅に住み続ける人はいないから、自分が介護施設に入ったら自宅を売却したいと考えているとしましょう。しかし、介護施設に入る時点で認知症になってしまっていると、自宅の売却をすることができないのです。もし、自宅の売却して得たお金を介護施設へ入所するための費用に当てようと考えていた場合には、入所費用も手に入れることができなくなってしまいます。
また、認知症の人は遺言を作成することもできません。一時的に判断能力が回復したタイミングで遺言を作成することもできますが、この場合には相続人同士で争いになってしまう可能性があるため注意が必要です。
例えば、作成した遺言が一部の相続人にとって不公平な内容だったとしたら、その相続人が「この遺言は亡くなった人が認知症の時に書いたものだから、無効になるはずだ。この遺言の通りに遺産分配はしない。」と主張する可能性があります。
こうなると、認知症の時に作成した遺言があるだけで、残された家族が相続争いに巻き込まれてしまう場合もあるのです。
このように、認知症になった後では、確実な相続対策を行うことができません。認知症になる前に、できる限りの争族対策をとっておくことが大切なのです。
では、認知症になる前にとっておくべき対策には、どのようなものがあるのでしょうか?
対策① 生前贈与
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他の人へ無償で譲り渡すことです。相続税を節税するために、生前贈与を活用しているという方も多いのではないでしょうか。実は、生前贈与は法律行為ですので、認知症になった後は行うことができません。
生前贈与は、相続税のかかる財産を減らしておくことができる、非常に有効な節税対策の1つです。早い段階で計画的に実行することで大幅な節税効果が期待できます。
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、多くの方が知っているのは暦年課税の方かと思います。
暦年課税とは、年間110万円までの贈与には贈与税がかからない課税方式の贈与制度です。この非課税枠110万円は贈与を受ける人1人ずつに与えられますので、例えば年間110万円の贈与を3人の子供に10年間行い、合計3,300万円もの財産を非課税で贈与することもできるのです。早いうちにコツコツと贈与をしておくことで、相続税をゼロに抑えることもできます。
一方で、相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与する際、合計2,500万円までであれば非課税で贈与することができる制度です。一見、暦年課税よりも一度に多くの財産を贈与税ゼロで贈与できるため、お得な制度のように思われますが、実はこの制度には贈与税がかからない分「相続税」がかかる仕組みになっているのです。
相続時精算課税で受け取った財産は、贈与をした人が亡くなったときに相続財産に加えられて相続税が課税されます。そのため、暦年課税のように相続税の節税効果はほとんどありません。
一度で財産を渡してしまいたい理由がある場合や、不動産などの分けられない財産を贈与する場合に活用されます。
対策② 遺言
遺言とは、主に自分が亡くなった後の財産承継について書き記した、いわば「最後の手紙」です。遺言は法定相続よりも優先されるため、遺言を残しておくことでその通りに財産を承継させることができます。
遺言の最大のメリットは、相続人同士の争いを未然に防ぐことができる点です。遺言のない相続では、相続人は遺産分割協議という話し合いを行って、「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決めることになります。この遺産分割協議は、相続人全員が納得して合意をしなければ成立しないため、誰か1人でも遺産分割の内容に納得できないという人がいると、協議を成立させることができません。このように、遺産分割協議は相続人全員の気持ちがまとまっていなければならず、争いの起こりやすい手続きなのです。特に、主な相続財産が自宅しかない場合や、元々相続人同士の仲が悪い場合、相続人の中に亡くなった人の介護をしていた人がいる場合には争いが起こりやすくなります。
しかし、遺言のある相続では、遺言の内容に沿って遺産分割を行うことができるため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありません。争いの起こりやすい手続きをなくすことで、円満な相続を実現することができるのです。
ただし、相続人全員の合意があった場合には、遺言に従わない遺産分割をすることも可能です。
さらに、遺言に「付言」を書いておくことも争族対策に効果的です。付言とは、家族への思いやメッセージのことです。付言に法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言にしたのか、どのような気持ちで遺言を書いたのかを記しておくことで、相続争いを防ぐことができます。
例えば、献身的に介護をしてくれた長女に、他の兄弟よりも多く財産を残してあげたいなど、片寄った遺言内容を望むケースがあります。しかし、このような内容では取り分の少ない兄弟が不満に思い、争いになる可能性があります。ですから、遺言の中に付言として「長女は献身的に私の介護を行ってくれたため、財産を多く残したい。他の兄弟にも納得して欲しい。」と書いておくことで、兄弟の不満を解消できることもあるのです。
遺言はただ残すだけでなく、どのような内容にするかが重要になります。認知症で判断能力が亡くなってしまうと遺言を作成することができません。判断能力があるうちは何度でも遺言を書き直すことができますので、早いうちに残しておくことをお勧めします。
ただし、遺言は、遺言を書いた人が亡くなったときに効力が発生します。ですから、亡くなる前の財産管理や承継、贈与について書いたとしても、法的な効力はありません。例えば、Aさんが「預金を息子に承継させる」と書いた場合、その預金が息子の名義になるのは、Aさんが亡くなった後です。もし、Aさんが認知症になり預金が凍結されてしまった場合には、Aさんが亡くなるまで息子は預金に手をつけることができないのです。亡くなる前から亡くなった後のことも考慮して財産の流れや使い道を決めておきたい場合には、「家族信託」という方法があります。家族信託については次の章でご説明いたします。
対策③ 家族信託
生前対策といえば、生前贈与や遺言をイメージする方も多いと思いますが、近年ではその中に「家族信託」が仲間入りし、関心を集めています。
家族信託とは、自分の財産の管理や処分、運用などを信頼できる家族に任せておく制度のことです。家族信託は、財産を預ける「委託者」と財産を預かる「受託者」、そして財産によって利益を受ける「受益者」の3人を設定して行います。認知症になった後の財産管理を目的に行いたい場合は、委託者と受益者を同じ人物(親)にすることで、親の財産を親のために管理する形を作ることができます。
例えば、Bさんは認知症対策として一緒に住む息子にBさん名義の自宅と預金を信託することにしました。この場合、委託者と受益者をBさん、受託者を息子にすることで、Bさんが認知症になった後でも息子がBさんの代わりに自宅を管理したり、預金を引き出したりすることができます。
また、家族信託は認知症対策としてではなく、亡くなった後の遺産承継としても活用することができます。Bさんが亡くなった時に信託を終了し、終了後に余った財産を息子に受け取ってもらう信託契約をしておくことで、遺言を書かなくても財産を確実に息子に承継させることができるのです。
「家族に任せるなら、認知症になったとでもできるでしょ。」と思われがちですが、家族信託では信託契約書を作成し、その契約書をもとに財産の名義変更なども行う必要があるため、立派な法律行為です。そのため、認知症になった後では家族信託を行うことができません。
家族信託は開始時期を自由に決めることができますので、早いうちに信託契約を結んでおいて、認知症になったら信託を開始することも可能です。
対策④ 任意後見制度
任意後見制度とは、将来自分が認知症になったときに備えて、信頼できる人に財産管理や身上監護を任せておくことができる制度です。財産管理や身上監護をしてくれる人のことを任意後見人と呼びます。この任意後見人が後見事務を開始できるのは、本人が認知症などにより判断能力が不十分になってからです。ですから、自分が認知症になったら誰に財産管理等をしてもらいたいかを考え、事前に任意後見契約を結んでおく必要があります。
未成年者や破産者以外であれば、誰でも任意後見人になることができます。任意後見人を選任しておくと、認知症になった後でも自分の代わりに任意後見人に預金を引き出してもらったり、必要に応じて不動産の売買や介護施設への入所手続きなどをしてもらうことが可能です。財産管理だけでなく身上監護も任せられるため、財産管理のみを任せられる家族信託よりもメリットの多い制度のように感じますが、実は任意後見制度にも大きなデメリットがあります。
1つは、認知症になってから任意後見制度がスタートすることです。家族信託では信託契約を結んだ時点で財産管理を任せることができますが、任意後見制度では認知症にならなければ財産管理等の事務を始めることができません。したがって、事業などの計画的な承継には活用が難しい制度です。
もう1つのデメリットは、毎月の報酬が発生する点です。家族信託の場合、財産を管理するのは信頼できる家族なので、報酬を支払わなくても契約が成立するケースが多くあります。しかし、任意後見制度の場合、任意後見人を依頼した専門家への報酬が発生します。また、報酬の発生しない親族に頼んだとしても、「任意後見監督人」への報酬が発生するのです。任意後見監督人とは、適切な財産管理が行われているかをチェックするために、家庭裁判所に選任された人のことです。主に司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることが多く、管理する財産額に応じて約1~3万円/月ほどかかります。
任意後見制度は、認知症になってからの自分を守るために効果的な制度です。しかし、毎月の費用がかかったりとデメリットもありますので、どのような方法で老後の自分を守っていくのが良いか、認知症になる前に検討しておきましょう。
生前対策で注意するべきポイントは?
認知症になる前にできる対策を4つご紹介いたしました。
・私が認知症になってしまったら、経営している会社はどうなるのだろう。
・私が死んだら、誰がこの家を引き継ぐのだろう。
老後や相続に関する問題は、持っている財産や家族構成によって人それぞれ異なります。しかし、このような問題を解決するときには、さまざまな側面から問題を見る必要があるのです。
例えば、認知症になった後の事業を長男に引き継がせるとして、自分が亡くなった後、さらに事業を引き継いだ長男が亡くなった後のことは考えていますか?また、自宅を誰に相続させたいかを考える際、相続人にかかる相続税の節税対策や、その人が亡くなった後のことも考えているでしょうか?
老後や相続の問題は、1つの側面からでは十分に解決することができません。自分が認知症になった後のことだけではなく、亡くなった後、さらに相続人が亡くなった後(二次相続)のことや、相続税の観点からも問題を解決していかなければならないのです。
さまざまな側面から相続対策を考えることは簡単なことではありません。相続対策をご検討の方は、相続に強い専門家に相談することをおすすめいたします。
まとめ
今回は、認知症になる前にしておくべき対策と、対策をとる際の注意点をご紹介いたしました。相続対策・認知症対策の多くは、認知症になってからではできません。自分の意思を明確にして、元気なうちから十分な対策をとっておきましょう。