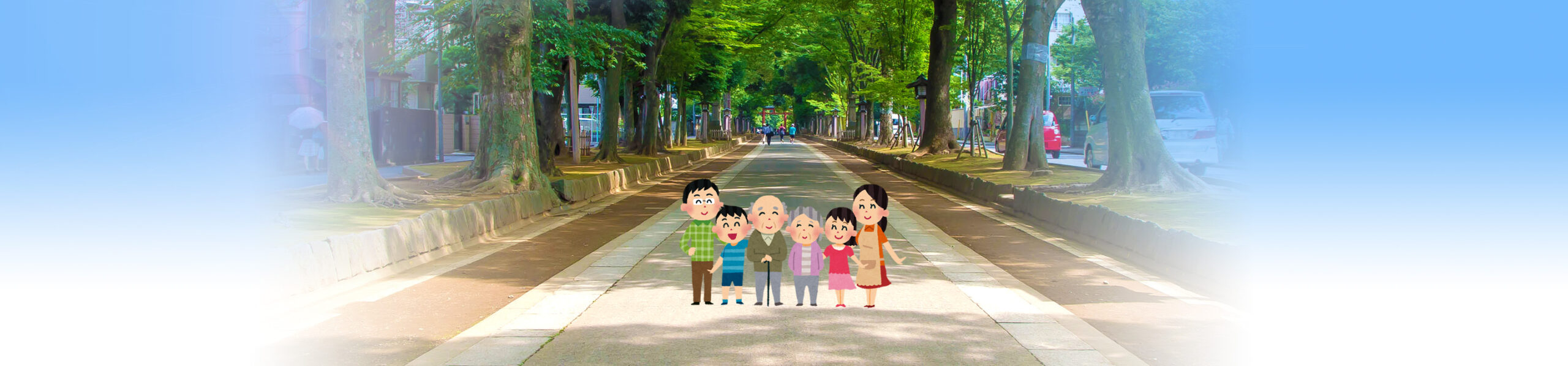近年、「終活」という言葉に関心が高まっており、それに伴って遺言やエンディングノートを活用する人が増えてきています。遺言やエンディングノートには、いずれも自分が亡くなった後はどのように使って欲しいかなどを書き記し、家族に自分の意思を伝える役割がありますが、「具体的にはなにが違うの?」と思っている人も多いのではないでしょうか。
実は、遺言とエンディングノートには大きな違いがあり、それを知らずに作成してしまうと、理想の相続対策ができない可能性もあるのです。あなたの思い描く相続対策を実現するために、遺言とエンディングノートの違いを理解しておきましょう。
この記事では、遺言とエンディングノートの違いや遺言が必要なケースについて、わかりやすくご説明しています。
遺言とエンディングノートって何が違うの?
遺言とエンディングノートにはどのような違いがあるのでしょうか?初めにそれぞれの特徴を確認し、違いについてご説明します。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、自分が亡くなった時に備えて、あらかじめ自分の想いや持っている財産などを書いておくノートです。最近ではエンディングノートを取り扱っている書店も増えてきていますが、自分で用意したノートを使っても構いません。
なにを書くか、どのように書くかは自由ですので、自分の気持ちを思いのままに書き留めておくことができます。
また、エンディングノートに葬式やその後の手続きのことを書き記しておくことで、残された家族が亡くなった人のエンディングノートを見ながら、スムーズに葬式や相続手続きを行うことができるのです。
遺言とは
一方で、遺言とは、主に自分が亡くなった後の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を記した書面のことをいいます。遺言には作成方法が決められており、遺言の種類によってその作成方法は異なります。
また、遺言は民法で決められている「法定相続」よりも優先するため、紛失や不備などがない限り、遺言の内容は亡くなった人の意思として法的に保証されます。つまり、遺言はエンディングノートよりも確実に希望の財産承継を行うことができるのです。
しかし、遺言には何を書いても良い、というわけではありません。遺言では法的な効力が認められる内容が決められており、これを「遺言事項」といいます。
代表的な遺言事項は以下のとおりです。
【法的な効力がある遺言事項】
・共同相続人の相続分の指定、または指定の委託
・遺産の分割方法の指定、または指定の委託
・遺産分割の禁止
・子の認知
遺言には、このほかにも様々な遺言事項が定められています。
遺言事項を知ることで、より確実な相続対策を行うことが可能です。
遺言に書ける14の遺言事項とは?
「自分が亡くなった後、持っている財産や事業を誰かに相続させたい。」このような想いは、遺言を書くことで実現することができます。
遺言とは、主に自分が亡くなった後の財産をどのように承継させるかについて書いた書面で、いわば「最後の手紙」のようなものです。遺言に書いた内容は法定相続よりも優先されるため、有効な遺言を残しておくとほとんどのケースで遺言の内容通りに遺産分割がされます。
しかし、遺言に書くことで法的な効力を持つ内容は遺産分割のことだけではありません。実は、遺言には財産のこと以外にも、法的な効力を持つ内容があるのです。これを「法定遺言事項」といいます。
法定遺言事項は以下のとおりです。
(1)共同相続人の相続分の指定または指定の委託
(2)遺産の分割方法の指定または指定の委託、遺産分割の禁止
(3)遺産分割における担保責任に関する定め
(4)遺留分侵害額請求の負担方法に関する定め
(5)遺贈
(6)特別受益の持ち戻し免除
(7)相続人の廃除・廃除の取り消し
(8)生命保険金の受取人の変更
(9)子の認知
(10)未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
(11)遺言執行者の指定または指定の委託
(12)信託の設定
(13)祭祀を主宰する人の指定
(14)一般財団法人の設立
遺言に書くことができる14の遺言事項について、1つずつ詳しくご説明していきます。遺言事項を理解し、自分に合った遺言を作成しましょう。
(1)共同相続人の相続分の指定または指定の委託
これは、一番よく知られている遺言事項の1つです。遺言では、自分の財産を法定相続分以外の相続分で分けることができます。
例えば、妻と子ども2人(長男と次男)がいるAさんの場合で考えてみましょう。妻と2人の子どもがAさんの財産を法定相続分で分けるとすると、以下のような割合で分割されます。
・妻の法定相続分:相続財産の2分の1
・長男の法定相続分:相続財産の4分の1
・次男の法定相続分:相続財産の4分の1
しかし、遺言に「妻に2分の1、長男に2分の1を相続させる」と記載すると、その通りに遺産分割がされるのです。遺言は法定相続よりも優先されるため、有効な遺言であれば相続人全員の同意がない限り、遺言通りの遺産分割がされます。
※法定相続人全員の同意があると、遺言に従わない遺産分割を行うことが可能です。
ただし、特定の法定相続人には遺留分があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人にのみ認められた最低限の相続分のことで、基本的には法定相続分の2分の1とされています。
遺言の内容に従って遺産分割をした際に、自分の取り分が遺留分に満たなかった場合には、他の相続人に対して遺留分侵害額を請求することが可能です。そのため、遺言を書く際には、法定相続人の遺留分を考慮した遺産分割となるように心がけましょう。
また、遺言では直接相続分の指定をするだけでなく、第三者に相続分の指定を委託することもできます。しかし、誰にでも相続分の指定を委託できるわけではありません。裁判所の判例では、相続人や包括受遺者には相続分の指定を委託することができないと解されています。そのため、多くの場合は、相続に詳しい司法書士や税理士などに委託します。
ただし、委託された第三者は委託を拒絶することができますので、遺言作成前にあらかじめ確認をとっておく必要があります。
(2)遺産の分割方法の指定または指定の委託、遺産分割の禁止
こちらも、よく遺言に書かれている内容の1つです。(1)は相続人間で割合的に差をつけるのに対し、こちらは具体的な財産内容で差をつけます。
例えば、「長男にはA不動産を、次男にはB不動産を相続させる」という書き方が遺産の分割方法の指定です。特に、遺言者名義の自宅に住んでいる長男に自宅を相続させたい場合や、事業を引き継ぐ次男に事業用財産や株式を相続させたい場合などは、この記載方法で指定します。
また、遺産の分割方法の指定は第三者に委託することが可能です。ただし、過去に相続人は第三者になることができない旨の判例が出ているため、第三者は司法書士等の専門家に委託する方が安全でしょう。なお、委託された第三者は委託を拒絶することができますので、遺言作成前にあらかじめ確認をとっておく必要があります。
さらに、遺言では遺産分割を禁止することも可能です。例えば、相続人の中に未成年者がいる場合や、相続人の関係が複雑で調査が必要な場合などに利用されるケースがあります。遺産分割の禁止は5年を超えない期間で定めることができます。
(3)遺産分割における担保責任に関する定め
民法上、遺産分割で相続した財産に欠陥があった場合に、他の相続人からその損失を補ってもらうことができると定められています。これは、相続人間の公平性を保つためです。
例えば、3,000万円の預金と評価額1,500万円の自宅を3人の子(長男、次男、三男)で分け合うケースで考えてみましょう。長男が1,500万円の自宅を、次男と三男が預金を1,500万円ずつ相続し、全員が公平に相続したように思えました。しかし、長男が相続した自宅には欠陥があり、実際の評価額は800万円だったのです。子の場合、長男は次男と三男に対して損害分を請求することができるのです。
遺言では、この担保責任を無効にしたり変更したりすることが可能です。例えば、遺言に「相続人は担保責任を負わない」旨の記載がある場合には、欠陥のある自宅を相続したとしても、次男と三男に損害賠償請求をすることができません。
(4)遺留分侵害額請求の負担方法に関する定め
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人にのみ認められる、最低限の取り分のことです。基本的に、遺留分は法定相続分の2分の1とされています。もし、遺産の取り分が遺留分よりも少ない場合には、他の相続人や受遺者に「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分に達するまでお金を請求することができるのです。
この遺留分を誰が負担するのかを、遺言で決めることができます。
遺留分を負担する順番は、遺贈の次に生前贈与と定められています。つまり、遺贈を受けた人と生前贈与を受けた人の両方がいる場合には、先に遺贈を受けた人に遺留分侵害額請求をしなければなりません。これは、遺言で順番を前後させることはできません。
しかし、遺贈を受けた人が複数人いる場合は、誰から先に負担することになるのでしょうか。
この順番を、遺言で指定することができるのです。
例えば、遺言に「遺留分の負担は先に受遺者A、次に受遺者Bとする。」と記載することで、遺留分の負担方法を指定することができるのです。
(5)遺贈
遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といいます。遺贈は遺言事項の中でも多く書かれる項目で、法定相続人以外の人に財産を渡したいときに活用されます。遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ記載方法が異なります。
包括遺贈とは、遺産の割合を指定して遺贈する方法です。
遺言には、「受遺者Aには遺産の3分の1を遺贈する」というように割合で記載します。
一方で、特定遺贈とは、特定の遺産を指定して遺贈する方法です。
遺言では、「受遺者Bには車を遺贈する」というように、具体的な財産を記載します。
包括遺贈は全ての遺産から包括的に受け取ることになるため、相続人と同じ扱いになります。従って、相続人と遺産分割の話し合いをする必要があります。また、遺言者に借金などのマイナスの財産がある場合には、マイナスの財産も遺贈されることになりますので注意が必要です。
特定遺贈の場合は、受け取る財産が指定されているため、相続人同士の話し合いへの参加は不要です。また、借金などのマイナスの財産を引き継ぐこともありません。
相続人以外へ遺贈をする場合は、どちらの方法が良いかを慎重に検討しましょう。
(6)特別受益の持ち戻し免除
特別受益とは、遺贈又は一定の生前贈与によって得た利益のことをいいます。相続では、このような利益を遺産に持ち戻してから遺産分割を行うことができます。
例えば、遺言者に2人の子ども(長男と次男)がおり、長男にのみ家の購入資金や結婚資金などを贈与してきたとします。しかし、これらの生前贈与を一切考慮せず、遺産を長男と次男で半分ずつ相続すると、次男にとって不公平な遺産分割となってしまいますよね。
このような場合に、民法では生前贈与などの特別受益を受けた相続人の相続分を減らすことで、長男と次男が公平に遺産を相続できるようにしています。これが「特別受益の持ち戻し」です。
しかし、遺言ではこの特別受益の持ち戻しを無くすことができます。相続人間で不公平な遺産分割となってしまいますが、生前贈与に意味を持たせたり、場合によっては相続トラブルを防いだりすることが可能です。
(7)相続人の廃除・廃除の取り消し
相続人の中に遺言者を虐待していたり、遺言者に対して重大な侮辱を与えたりする人がいる場合には、その相続人の相続権を剥奪することができます。これを「相続人の廃除」といいます。
例えば、「長男から長年暴言や暴力を受けていた。」「妻が愛人と同棲していて全く家に帰って来ず、子どもたちの面倒も見ない。」というケースでは廃除が認められる可能性が高いです。
相続人の廃除は、家庭裁判所に申し立てをして行います。遺言者本人が生きているうちに申し立てる方法もありますが、遺言で廃除をすることも可能です。遺言で廃除を行う場合は、遺言執行者を指定する必要がありますのでご注意ください。
また、すでに廃除をした相続人が改心し、廃除を取り消したい場合には、遺言で廃除の取り消しを行うこともできます。廃除の取り消しがされた相続人には再び相続権が与えられ、他の相続人と同じように遺産を相続することができます。
(8)生命保険金の受取人の変更
遺言では、生命保険金の受取人を変更することができます。
生命保険金は民法上は相続財産には含まれませんが、相続税を計算する上では、相続財産として扱われる財産です。そのため、相続税はかかるが遺産分割の対象とはならず、受取人固有の財産となります。
遺言で生命保険金の受取人を変更する場合、新たな受取人は相続人である必要はありません。例えば、孫や内縁の妻など、相続人以外の人を受取人に設定することができます。
ただし、遺言で受取人を変更すると、それを知った元受取人は納得いかないでしょう。元受取人が遺言を破棄したり、保険会社への通知をしなかったりする可能性が考えられます。トラブルを防ぐためには、生前に変更を済ませる方が良いですが、遺言で変更する場合は遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
(9)子の認知
遺言では子の認知も行うことができます。
認知とは、婚姻関係にない夫婦の間に生まれた「非嫡出子」に対して、父が「この子どもは私の子どもだ。」と親子関係を認めることをいいます。母は認知を行わずとも親子関係が認められるのですが、父の場合は認知の手続きを行わなければ親子関係が認められません。認知をすることにより、認知された子も法定相続人となりますので、遺言での認知は非常に重要な項目となります。
例えば、遺言者に子どもがおらず、兄がいる場合には、兄のみが法定相続人となります。しかし、遺言者が遺言によって子の認知をした場合、認知された子が遺言者の法定相続人となり、兄は法定相続人ではなくなるのです。
そのため、認知により他の相続人にどのような影響があるのかを考慮して、トラブルにならないようにしましょう。
なお、遺言で認知を行う場合は、遺言執行者を指定する必要があります。
(10)未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
未成年に親権を行うものがいなくなってしまう場合、遺言で「未成年後見人」や「未成年後見監督人」を指定することができます。民法では20歳未満(令和4年4月1日からは18歳未満)の人を未成年としています。
未成年後見人とは、親権者が亡くなる等の理由で未成年に対して親権を行う人がいない場合に選任される人のことです。主に、未成年者の監護養育や財産管理、契約などの法律行為を行う役割があります。
一方で、未成年後見監督人とは、未成年後見人が未成年者の不利にならないように事務を行っているかをチェックする人のことです。ただし、必ず選任しなければならないわけではありません。
例えば、子どもが生まれてから離婚し、親権を父が持った場合では、父が亡くなると未成年の子どもに親権を行うものがいなくなってしまいます。このような場合に、父は遺言で未成年後見人を指定しておくことができるのです。
(11)遺言執行者の指定または指定の委託
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人を代表して相続手続きなどを進める人のことです。例えば、預金や不動産の名義変更や財産目録の作成を行います。
遺言がない場合は遺言執行者を指定する必要はありません。しかし、遺言の内容によっては「遺言執行者がいた方が良いケース」と、「遺言執行者が必要なケース」がありますので注意が必要です。
・遺言執行者がいた方が良いケース
相続では、預金や不動産の名義変更を行うときに、相続人全員の印鑑証明書や署名押印が必要になるため、非常に時間と労力がかかります。特に、相続人が多く関係が複雑な場合や、相続人の中に遠方に住んでいる人がいる場合には、手続きが長引いてしまうこともあるのです。
しかし、遺言執行者を指定しておくと、必要な印鑑証明書と署名押印は遺言執行者のみで足ります。そのため、さまざまな手続きを単独で行うことができ、スムーズな相続を実現することができるのです。
・遺言執行者が必要なケース
遺言書に「相続人の廃除・廃除の取り消し」や「子の認知」について記載する場合には、遺言執行者が必要になります。
遺言では直接遺言執行者を指定する方法のほかに、第三者に遺言執行者を指定してもらう方法があります。これは、遺言を作成したときと、相続が発生したときで状況が異なっている可能性があるからです。例えば、遺言執行者に指定した人が連絡が取れなくなってしまう場合や、相続発生前に亡くなっている場合も考えられます。そのため、遺言者の相続発生時に最も相応しい遺言執行者を指定できるように、第三者へ指定を委託することができるのです。
また、遺言での指定がない場合には、相続人などが家庭裁判所へ申し立てることで、後から遺言執行者を選任することができます。廃除や認知についての記載があるのに遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に選任を申し立てましょう。
(12)信託の設定
信託には様々なものがありますが、この場合の信託とは、自分の財産を信頼できる人に預けて管理してもらう制度のことを指しています。
信託では、財産を預ける「委託者」と財産を預かる「受託者」、信託行為で発生した利益を受けられる「受益者」の3人が登場します。例えば、父(委託者)が預金2,000万円を長男(受託者)に預け、障害を持っている次男(受益者)のために管理してもらう、という形を作ることができます。
このような信託を遺言で設定することができるのです。
遺言で信託の設定をした場合、遺言者が亡くなったときに信託が開始します。「自分が亡くなった後の妻(夫)の生活が心配。」、「障害を持った子どもへの資金援助を家族に引き継ぎたい。」という場合には、信託をすることで解決できる可能性があります。
(13)祭祀(さいし)を主宰する人の指定
仏教の家系であれば、仏壇や位牌、墓跡などを持っているかと思います。このような財産を「祭祀財産」といいますが、祭祀財産は他の財産とは区別して扱われるため、遺産分割の対象となりません。
祭祀財産は原則として、その家や地域の慣習に従い、祭祀を主宰するべき者が承継することになっています。ただし、遺言で指定があれば、その人が祭祀財産を承継します。
なお、遺言による指定がなく、慣習も不明の場合には、家庭裁判所で祭祀財産の承継者を指定することができます。
(14)一般財団法人の設立
遺言では自分の財産をお世話になった団体に寄付したり、自分の意思で一般財団法人を設立することができます。
一般財団法人とは、財産の法人格を与えて作られた組織のことです。設立の手続きは以下のとおりです。
①設立する人が、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める
②遺言執行者が遺言の内容通りに手続きを進め、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成し、公証人の認証を受ける
③遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
④定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含む)を定めていない場合は、定款の定めに従って、これらの者を選任する
⑤設立時理事及び設立時監事が設立手続きの調査をする
⑥設立時理事が法人の代表者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う(設立登記申請日が法人格取得の日となります)
なお、遺言で一般財団法人を設立する場合は、遺言執行者の指定が必要です。
遺言に書くことができる14の遺言事項についてご説明しました。遺言は主に財産について書くものだと思っている人が多いのですが、実は財産以外にも様々な内容を書くことができます。
自分に合った遺言を作成したい方は、相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
遺言とエンディングノートの違い
遺言とエンディングノートの大きな違いは、法的な効力があるかどうかです。
エンディングノートに書いた内容には法的な効力がなく、残された家族がその内容に従う必要はありません。しかし、遺言には法的な効力があるため、残された家族は遺言の内容に従って財産を相続することになります。なお、遺言に不備がある場合や、相続人全員が同意した場合には、遺言の内容に従わない相続も可能です。
自分の希望を書くだけならエンディングノートで十分と思われる人も多いかと思いますが、法的効力のある遺言を書いておくことで、残された家族の争族対策を行うことができます。
遺言のない相続では、相続人同士で遺産分割協議という話し合いを行って、「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決めることになります。遺産分割協議は相続人全員が遺産分割の内容に同意することで成立するのですが、実はこの話し合いの中で争いが起こるケースが非常に多いのです。
例えば、亡くなった人に長男と次男がおり、長男は亡くなった人の介護を行ってきたが、次男は一切介護をしなかったというケースでは、長男が「介護をしてきた分、遺産を多くもらえるはずだ。」と主張をして争いになる可能性があります。
このように、遺産分割協議では遺産を巡って争いとなることが多く、一度争いに発展してしまうと解決に時間がかかってしまうケースも珍しくありません。
しかし、遺言を作成すると遺言の内容に従って遺産分割がされるため、相続人同士での遺産分割協議は不要となります。そのため、遺産を巡って意見の対立が起こることが少ないのです。また、多少不公平な遺産分割であっても、「亡くなった人の意思だから」と納得できることもあります。
このような争族対策は、法的効力のないエンディングノートではできません。少しでも相続に不安のある方は、遺言の作成をご検討ください。
遺言が必要な5つのケース
ここでは、遺言が必要なケースをいくつかご紹介いたします。
1つでも当てはまる人は、遺言の作成をお勧めします。
ケース① 主な相続財産が不動産のみ
「相続財産は自宅と少しの預金だけ」
このような場合には遺言が必要です。不動産は簡単に分けることができないため、遺産分割協議がなかなか成立しないケースが多くあります。
特に、相続人の中に亡くなった人の自宅に住んでいる人がいると、「自宅を売却して得たお金を分け合いたい」という意見と「自宅に住み続けたいから売却したくない」という意見が対立し、争いに発展してしまうケースもあります。
主な財産が不動産のみの場合には、あらかじめ家族と話し合い、遺言を残しておく必要があります。
ケース② 相続させたくない人がいる
「お金の無駄遣いが激しく親に迷惑をかけている子どもがいる」
「暴力や暴言により苦痛を与える配偶者がいる」
このような相続人に財産を相続させたくない場合には、遺言によりその人の相続分を減らすことができます。
しかし、いくら遺言で相続分を減らしたとしても、遺留分を請求されると財産を渡さなければなりません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の相続分で、一般的に法定相続分の2分の1とされています。つまり、相続させたくない人にも、法定相続分の半分までは相続する権利があるのです。
そこで、相続分をゼロにしたいという場合には、「相続廃除」をして、その人の相続権を無くすことができます。相続廃除は、被相続人(亡くなった人)本人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをして行う方法と、遺言により行う方法があります。
相続廃除の対象となる人は、民法第892条で以下のように定められています。
『遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる』
つまり、家庭裁判所へ申し立てをすることで、被相続人に虐待や侮辱を加える相続人や、著しい非行をしていた相続人の相続権を無くすことができるのです。遺言で相続廃除をする場合には、遺言執行者の指定をする必要がありますのでご注意ください。
ケース③ 子どものいない夫婦
子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合は、相続争いになることが多いため遺言が必要です。
亡くなった人の法定相続人には順位があり、高い順位の人から相続権が与えられる仕組みになっています。法定相続の順位は以下のとおりです。
|
相続順位 |
法定相続人 |
それぞれの法定相続分 |
|
第1順位 |
子どもと配偶者 |
子ども1/2、配偶者1/2 |
|
第2順位 |
直系尊属(父母や祖父母)と配偶者 |
直系尊属1/3、配偶者2/3 |
|
第3順位 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹1/4、配偶者3/4 |
この表から、亡くなった人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人となりますが、子供がいない場合には、配偶者の他に親や兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
例えば、亡くなった夫(妻)と仲の悪かった兄弟姉妹が相続分を主張してきた時、争うことなく遺産分割協議を成立させることができるでしょうか。もし、遺産分割協議が成立しなかった場合には、妻(夫)は夫(妻)名義の自宅を自分の名義に変更することができません。
このような場合には、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言を作成しておくことで、争いを防ぐことができます。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、不公平な遺言でも遺留分を請求されることがありません。
ケース④ 法定相続人以外の人に財産を渡したい
「隣人が身の回りの世話をしてくれて助かっている」
「内縁の妻に財産を渡したい」
このような場合には、遺言を作成することで財産を渡すことができます。隣人や内縁関係の人には相続権がありません。そのため、遺言を書いておかなければ、財産を渡すことができないのです。
遺言により財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。遺贈の方法には、大きく分けて特定遺贈と包括遺贈の2つがありますが、争族対策の面では特定遺贈をお勧めします。
特定遺贈とは、特定の財産を遺贈する方法です。例えば、「〇〇銀行の預金を内縁の妻Bに遺贈する」など、1つの財産を指定して記載します。そのため、対象となる財産の情報をしっかり記載しておく必要があります。
一方で、包括遺贈とは、全部または一部の財産の中から一定の割合で遺贈する方法です。例えば、「私の財産の4分の1を内縁の妻Bに遺贈する」というように記載します。
包括遺贈は特定遺贈とは異なり、受遺者に他の相続人と同じ権利義務が与えられるため、もし亡くなった人に借金がある場合には、その借金も負担する必要があるのです。また、包括遺贈の受遺者は遺産分割協議に参加して、どの財産を受け取るかを話し合わなければなりません。
このような点から、遺贈をする場合は包括遺贈ではなく特定遺贈で行うことをお勧めします。
ケース⑤ 特定の相続人に事業を相続させたい
事業を行っている場合には、遺言で事業承継を行うことができます。事業で使う事務所や自動車、机なども相続財産となります。そのため、遺言を作成しなければ、相続人の誰でも事業用財産を相続することができるのです。ですから、遺言で誰にどの財産を相続させるかを指定しておくことで、安心して事業承継を行うことができます。
また、自社株を所有している場合には、株式の承継にも注意が必要です。複数の相続人が株式を持っている状態だと、承継後の経営に影響が出てしまう可能性があります。そのため、「自社株はすべて後継者となる人が相続する」などの記載をしておく必要があります。
法的な効力がある遺言を作っておきましょう
遺言はエンディングノートとは違って法的な効力があることから、より確実な遺産承継をすることができます。また、相続人同士で話し合う遺産分割協議をする必要もないため、残された家族の相続争いを防ぐことも可能です。
「私の家族はみんな仲が良いから大丈夫。」
「相続争いってお金持ちの家しか関係ないでしょ?」
と勘違いしている人も多いのですが、実は、相続では仲が良く資産の少ない家庭でも争いが起こるケースは珍しくありません。
裁判所の司法統計によると、「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」の内訳は、約3割が財産額1,000万円以下の家庭となっており、財産額5,000万円以下では7割以上を占めていることがわかりました。つまり、財産額が少ないほど争いが起こりやすい傾向にあるという結果になっています。
また、仲の良い兄弟でもお金が絡むと争いになるケースも多く、相続で発生した争いはなかなか解決できないこともあります。
遺言を有効に活用して、争いなく相続手続きを終えられるように対策をとっておくことが大切です。
そうは言っても、実際に紙とペンを用意して考えてみると、うまく考えがまとまらず、どうすれば良いかわからない、という人も多いのではないでしょうか。遺言は何度でも書き直しができますので、まずは自分の持っている財産を把握し、誰に相続させたいかをシミュレーションすることから始めてみましょう。
争族対策や節税対策など、どのような対策を取るかによって遺言の内容は異なります。あなたに合った遺言を作成するためには、相続に強い専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
今回は、遺言とエンディングノートの違いや遺言が必要なケースについてご説明しました。法的効力のある遺言は、自分の思い通りの遺産承継が実現できるだけでなく、残された家族の相続争いの防止にもつながります。
円満でスムーズな相続のために、元気なうちに遺言を作成しておきましょう。