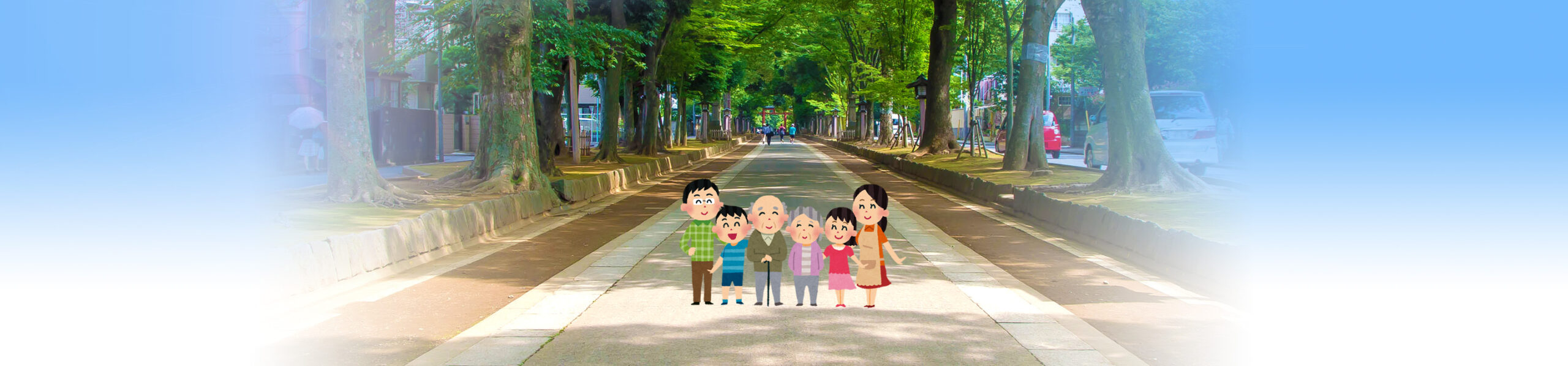相続や終活について調べたとき、「生前贈与」という方法をよく目にするかと思います。生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他人に譲り渡し、相続財産をあらかじめ減らしておくことができる相続税対策の1つです。
今回は、相続対策に使える贈与制度をいくつかご紹介いたします。生前贈与をうまく活用して、大幅な節税と円満な相続を実現しましょう。
なぜ生前贈与が相続対策になるのか
生前贈与が相続税の対策に有効な理由をお話しする前に、まずは相続税の仕組みについてお話しいたします。
相続により亡くなった人の財産が他の人に移転すると、財産額に応じた「相続税」が課税されます。しかし、この相続税には基礎控除と呼ばれるボーダーラインがあり、このボーダーラインを超える場合にのみ相続税が課税される仕組みになっているのです。
相続税の基礎控除額は以下の算式で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、亡くなった人に妻と2人の子がいる場合、法定相続人は3人となります。したがって、この場合の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。亡くなった人の相続財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないのですが、4,800万円を超えている場合は、超えている部分に相続税が課税されるのです。
例えば、亡くなった人が1億円の財産を持っていたとしましょう。法定相続人が3人の場合には、基礎控除額を大幅に超えているため相続税が発生します。
※財産の分け方によっては相続税が発生しない場合もあります。
財産を残す人にとっても、残される人にとっても、支払う相続税はできるだけ減らしたいですよね。
このように相続税を抑えたいケースでは、生前贈与は有効な手段の1つなのです。
本来、自分の財産を他人に贈与すると、その財産を受け取った人に対して「贈与税」が課税されます。せっかく相続税の対策として贈与を行ったとしても、贈与税が課税されてしまっては節税対策の意味がありません。しかし、贈与税には一定額以下の贈与には贈与税が発生しない制度や特例があり、うまく活用することで贈与税を支払わずに財産を移転することができるのです。
また、計画的に生前贈与を行うことで、あらかじめ相続財産を子や妻に移転しておくことができるため、相続税の節税にもつながります。
【贈与のキホン】暦年課税と相続時精算課税について
贈与を活用して相続対策は、2つの贈与制度のうちどちらかを選んで行うことになります。それが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。この2つは贈与税が課税される仕組みが異なります。
「暦年課税」とは、年間110万円までは贈与税を支払わずに贈与できる制度です。生前贈与と聞くと、こちらの制度をイメージする方が多いのではないでしょうか。
贈与税は財産を受け取る側(受贈者)に課される税金です。したがって、贈与を受ける人ごとに毎年110万円の控除を利用することができます。例えば、3人の子に毎年110万円ずつ、10年間にわたって贈与を行ったとすると、3人×110万円×10年間=3,300万円もの財産を無税で贈与することができるのです。
暦年課税は、早いうちから計画的に行うことで効果の高くなる相続対策です。
なお、暦年課税を利用して贈与された財産は、「3年以内加算」により相続税の対象となる場合がありますのでご注意ください。3年以内加算については、後ほどご説明いたします。
一方で、相続時精算課税とは、2,500万円までの贈与には贈与税がかからない制度です。大きい財産を一気に贈与することができるため、暦年課税よりもお得な制度だと思われがちですが、実はこの制度の利用には条件があります。
相続時精算課税を利用することができるのは、「60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対する贈与」のみと定められています。さらに、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに相続財産に加えられ、相続税の課税対象になってしまいます。
そのため、贈与税の節税にはなりますが、相続税の節税には向いていない制度なのです。
しかし、「確実に継がせたいから、生きているうちに財産を移転しておきたい」などの理由がある場合には、争族対策として有効な手段となります。
暦年課税と相続時精算課税は併用することができません。一度相続時精算課税を利用して贈与を受けると、暦年課税に変更することができなくなってしまいますので、どちらの制度が良いか慎重に考慮しましょう。
相続対策に使える贈与税の特例
暦年課税と相続時精算課税の他にも、贈与には贈与税が非課税となるさまざまな特例があります。
①贈与税の配偶者控除
②教育資金の一括贈与
③住宅取得等資金の贈与
④結婚・子育て資金の一括贈与
上記の制度について、詳しくご説明していきます。
①贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための費用の贈与を行う場合、基礎控除110万円の他に最大で2,000万円までの控除が受けられる特例です。
この特例の適用を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上の夫婦に限られます。
例えば、婚姻期間25年のAさん夫婦は、3,000万円の自宅の購入を検討しています。購入代金のうち、Aさんが2,000万円、妻が1,000万円を負担することにしました。この場合、妻がAさんに対して1,000万円の贈与を行なったとしても、「贈与税の配偶者控除」を適用すれば、贈与税ゼロで贈与をすることができるのです。
ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用財産に住み始め、その後も住み続ける予定であることが要件となります。「贈与税の配偶者控除を利用して買った不動産に住む予定がない。」という場合には特例の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
贈与税の配偶者控除は、一度に大きなお金を配偶者に贈与することができるため、節税に有効であると思う人も多いのではないでしょうか。しかし、この特例は相続税の軽減にはほとんど効果がありません。
夫(妻)が亡くなった場合、残された配偶者は「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用することで相続税を大幅に節税することができます。
②教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与とは、簡単に言うと、30歳未満の人が教育資金に充てるために、父母や祖父母などの直系尊属から金銭的な援助を受けた場合、そのうち1,500万円までの部分は非課税となる制度です。なお、学校等以外のものに支払われるお金の場合、非課税限度額は500万円となります。
この制度は他の制度とは異なり、贈与を受ける人(受贈者)から贈与をする人(贈与者)へ、直接お金を渡しただけでは成立しない点に注意が必要です。教育資金の一括贈与を利用して子や孫にお金を贈与する場合には、初めに信託銀行などの金融機関にお金を預け、受贈者がその金融機関に対して必要な書類を提出することで、お金を預かった金融機関から受贈者に対して教育資金が渡されることになります。金融機関がお金の管理をしてくれるため、毎月一定額の贈与をすることも可能です。
非課税となる教育資金には、以下のものが含まれます。
・入学金や授業料など
・学習塾や習い事の教室にかかる費用
・通学定期券の費用、留学費
幼稚園から大学まで、教育にはさまざまな費用がかかります。「孫のために何か応援したい」と考えている方に是非利用していただきたい制度です。ただし、教育資金の一括贈与は、2023年3月31日までの贈与が対象となります。期間を過ぎた場合には制度を利用することができませんので、ご注意ください。
③住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫への贈与へ、自己の居住の用に供する住宅の新築や取得、増改築のためのお金を贈与した場合、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度です。つまり、マイホームを買うときに親から資金援助を受ける、という場合にお得に贈与が受けられる制度なのです。
この制度は、2021年末に終了する予定だったのですが、令和4年の税制改正大綱により2023年末まで延長されることになりました。
贈与税の非課税限度額は以下のとおりです。
|
住宅の形態 |
非課税限度額 |
|
省エネ等住宅 |
1,000万円 |
|
上記以外の住宅 |
500万円 |
省エネ住宅とは、バリアフリーや耐震性、耐熱性に優れた住宅のことです。住宅性能証明書など、省エネ住宅であることを証明できる書類を贈与税の申告書に添付することで、非課税限度額を1,000万円に引き上げることができます。
住宅取得等資金の贈与を利用するには、制度の適用を受ける住宅と贈与を受ける人(受贈者)がいくつかの要件を満たしている必要があります。安心して制度を利用できるように、あらかじめ要件を確認しておきましょう。
④結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与とは、簡単にいうと、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の人へ、結婚・子育て資金を贈与した場合に、最大1,000万円までであれば非課税で贈与できる制度です。
この制度も教育資金の一括贈与と同様に、贈与者から受贈者へ直接お金を渡しただけでは成立しない点に注意しましょう。結婚・子育て資金の一括贈与を利用して子や孫にお金を贈与する場合には、初めに信託銀行などの金融機関にお金を預け、受贈者がその金融機関に対して必要な書類を提出することで、お金を預かった金融機関から受贈者に対して結婚・子育て資金が渡されることになります。金融機関がお金の管理をしてくれるため、毎月一定額の贈与をすることも可能です。
非課税となる結婚・子育て資金には、以下のものが含まれます。
・挙式費用や新居にかかる費用(上限300万円)
・不妊治療や妊婦健診にかかる費用
・子どもの医療費、幼稚園や保育園にかかる保育料
挙式費用や新居にかかる費用は上限が300万円となりますので、注意が必要です。「子どもや孫が結婚するから、お祝いをしたい。」という方に是非利用していただきたい制度です。ただし、結婚・子育て資金の一括贈与はを利用するためには、いくつかの要件を満たしている必要がありますので、あらかじめ要件を確認しておきましょう。
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与はうまく活用することで、大幅な節税対策を実現することが可能になります。ただ「贈与しておけばいいんでしょ。」と何も考えずに生前贈与をしてしまうと、節税対策にならないほか、相続人同士の争いを招いてしまう恐れもあるのです。
ここでは、生前贈与で節税対策・争族対策を行うために注意するべき点をご説明いたします。
①亡くなる前3年以内の贈与には相続税がかかる
亡くなる前3年以内にされた贈与はなかったものとみなされ、相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象となってしまいます。ですから、相続税の節税のために駆け込みで生前贈与をしたとしても、その贈与には意味がないのです。
例えば、持病のあるBさんが、節税対策のために長男と次男に110万円ずつ贈与をしたとします。しかし、その贈与から2年後、Bさんは持病が悪化して亡くなってしまいました。Bさんには、亡くなった時点で2,000万円の預金がありました。
この場合、Bさんが亡くなる2年前に行った生前贈与は、相続財産へ持ち戻されますので、Bさんの相続財産は合計で2,000万円(預金)+220万円(贈与財産)=2,220万円となります。
このように、節税対策のために生前贈与を行ったとしても、その贈与から3年以内に亡くなった場合には、節税対策の意味がなくなってしまいます。そのため、節税対策として生前贈与を行う場合は、元気なうちからコツコツと行う必要があるのです。
制度をうまく活用して、効果的な節税を実現しましょう。
②贈与をすることで相続人同士のトラブルを招く恐れがある
生前贈与は主に、贈与税や相続税の節税対策として利用されていますが、よく考えずに生前贈与をしてしまうと、思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
例えば、長男と次男のいるCさんは、長男にのみ留学費用や結婚資金として贈与を繰り返してきました。そんな中、Cさんが預金6,000万円を残して亡くなってしまいました。
長男は「法定相続通りに長男と次男で3,000万円ずつ分けよう。」と主張しましたが、次男はそれに納得できません。
次男は「兄さんは留学費用や結婚資金の贈与を受けていたが、自分はバイトや仕事で稼いだお金だけで留学や結婚資金を準備した。なのに、相続財産を半分ずつ分けるなんて不公平だ。」と主張しました。
しかし、長男はCさんの生前に様々な贈与を受けていたことを気にしておらず、「自分の相続分は譲らない。」と言います。長男と次男がお互いの主張を譲らないため、最終的には弁護士の介入によりトラブルを解決することになりました。
このように、偏った生前贈与があると、相続が発生したときに相続人同士が相続分を巡って争いになる可能性があります。それは仲の良い兄弟や遺産の少ない家庭でも同じです。「ウチは兄弟仲が良いから大丈夫。」と思わずに、元気なうちから争族対策をしておきましょう。
生前贈与だけでなく遺言や家族信託も活用しましょう
計画的な生前贈与は、残された家族の相続税申告や納税の手間をなくし、スムーズな相続手続きを実現することができます。しかし、残された家族が相続トラブルに巻き込まれないためには、生前贈与だけでは足りないケースもあるのです。
例えば、亡くなる前の財産管理については、遺言や家族信託などの制度を活用して対策を取る必要があります。特に、一部の相続人にのみ生前贈与を繰り返しており、相続人の間に不公平が生じてしまう恐れがある場合には、トラブルとなる可能性が十分にあります。
相続税対策をとっていたとしても、争族対策が取れていなければ意味がありません。相続での争いは一生解決しないこともありますので、家族が相続トラブルに巻き込まれないよう、元気なうちから遺言や家族信託を活用した争族対策をしておきましょう。
まとめ
今回は、相続対策に使える生前贈与の制度をいくつかご紹介しました。最大の節税効果を得るには、早いうちから計画的に生前贈与を行うことが有効です。ただし、相続対策の三原則「節税対策」「納税資金対策」「争族対策」をもれなく行うためには、生前贈与だけでなく遺言や家族信託なども併用することが大切です。
相続対策をご検討の方は、相続に詳しい専門家へご相談ください。